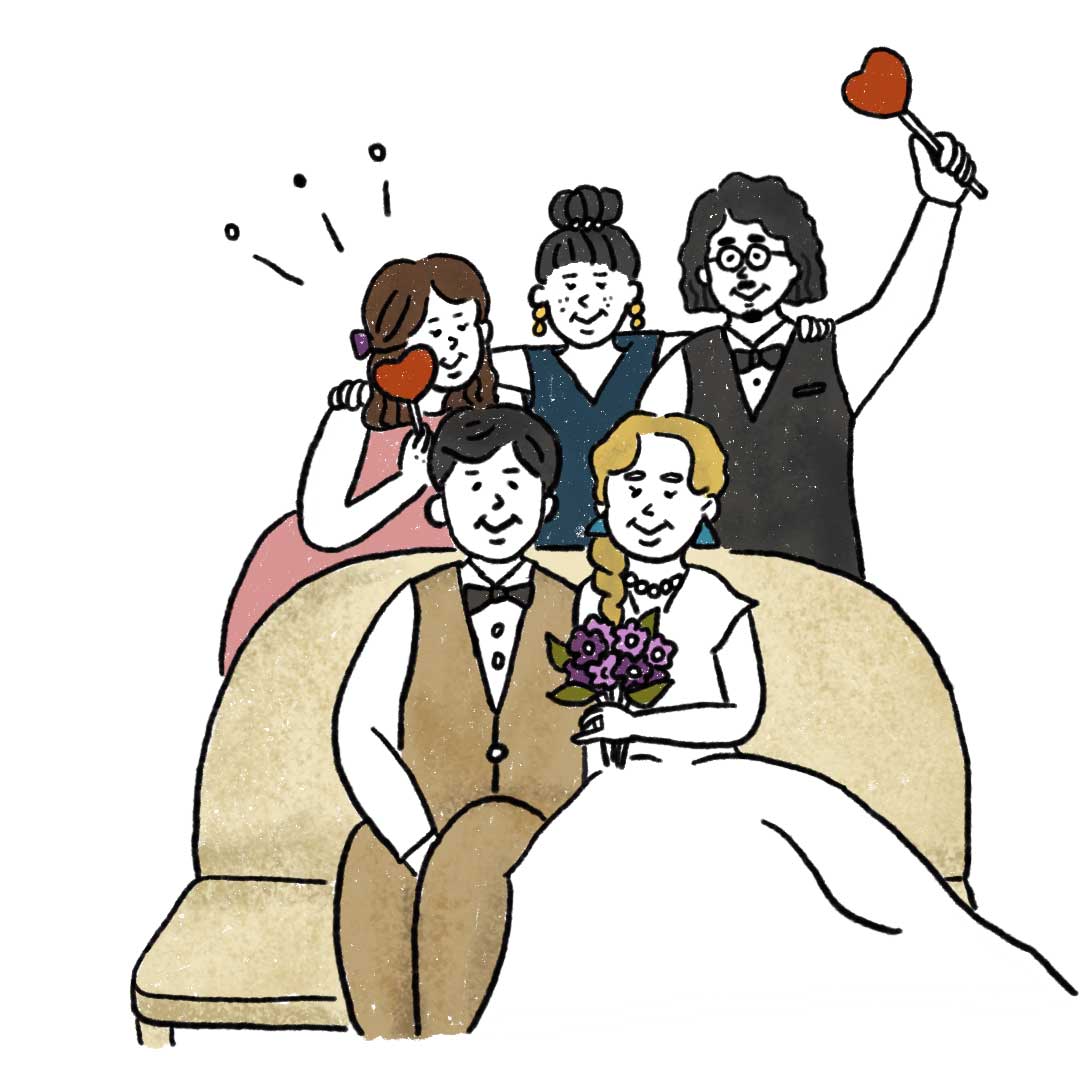兄弟・姉妹へのご祝儀はいくら包むのが正解?金額相場や渡し方のマナーも解説

兄弟や姉妹が結婚!おめでたいけれど、気になるのはご祝儀のこと。いくら包めばいいの?渡すタイミングは?
この記事では、兄弟・姉妹へのご祝儀の相場や渡し方、よくある疑問について解説します。これで、あなたもスマートにお祝いの気持ちを伝えられます!
目次
兄弟や姉妹の結婚にご祝儀は必要
兄弟や姉妹の結婚式には、ご祝儀は必要なのでしょうか?
結論から言うと、基本的には必要です。しかし、兄弟・姉妹との関係性や環境によっては、必ずしもご祝儀という形である必要はありません。
兄弟・姉妹との関係性や環境によっても異なる
基本的には一般的な結婚式と同じく、兄弟や姉妹の結婚式に対してもご祝儀を包む必要があります。
ただし包む側がまだ若く学生であったり、両親と同居していたりする場合、引出物は両親とまとめてひとつにすることも。その場合はご祝儀を包まなくても大丈夫です。
ご祝儀の代わりに結婚祝いのプレゼントを渡す場合も
ご祝儀の代わりに、新郎新婦が欲しいものを直接プレゼントするという方法もあります。事前に欲しいものを聞いておくか、ギフトカタログなどを贈るのも良いでしょう。
ただし、ご祝儀を渡さない場合は、事前に兄弟・姉妹に相談し、理解を得ておくことが大切です。また、結婚式当日は、お祝いの気持ちを込めて、心からの祝福の言葉を伝えましょう。
兄弟・姉妹へのご祝儀の相場はいくら?ケース別に紹介

この章では、兄弟・姉妹の結婚におけるご祝儀の相場について詳しく解説していきます。
贈る側が未婚の場合:3万~5万円
贈る側がまだ未婚なら、ご祝儀の金額は相場通りの5万円ほどでOK。
まだ年齢が若く、社会人になりたてという場合や、結婚するのが兄や姉の場合は、3万円程度でも大丈夫とされています。
贈る側が既婚(夫婦)の場合:7万~10万円
贈る側が既婚の場合、夫婦で招待されることも多いですよね。さらに子供が一緒に出席する場合は、食事代として、子供の年齢に応じて5000円から1万円程度を足します。
また、夫婦のどちらかが欠席する場合などは、相場額から差し引いた入りせず、そのまま渡すのが一般的なようです。
ご祝儀の金額相場としては、だいたい7~10万円程度ですが、自分の結婚のときにもらった金額と同額を渡すのが基本。
ただし、新郎新婦が弟や妹の場合、相場より少し多めに包むことも多いようです。ご祝儀袋には、夫のフルネームと左横に妻の名前を書いて渡しましょう。
贈る側が夫婦+子供2人(家族4人)の場合:10万~15万円
家族4人で結婚式に出席する場合、ご祝儀の相場は10万円から15万円が一般的です。
夫婦2人の場合の相場に加え、子供2人分の食事代として、それぞれ5,000円から1万円程度を加算して考えましょう。
学生や親と同居の場合:個人で包まなくても大丈夫
自分が両親と同居している場合や、まだ学生という場合、両親と同一世帯として招待されることが多いですよね。
その場合、ご祝儀は一世帯に一つなので、個人で包む必要はありません。
お祝いの気持ちを伝えるなら、何か兄弟姉妹が喜びそうな結婚祝いを贈るのもアリですよ。
地域や家族によって独自の慣習がある場合も
今までお話ししたのは、あくまで一般的な考え方。でも親族間では、ご祝儀に関して独自のルールがある場合も少なくありません。
例えば、「兄弟姉妹間は、一律5万円」「お互いご祝儀はなしにしよう」など、今までの慣例がある場合もあるんです。
一人で考える前にまずは両親に確認してから、ご祝儀の額を決めると安心ですよ。
贈る相手が再婚の場合:基本は相場通りでOK
再婚の場合でも、おめでたいことには変わりないので、相場通りの金額を渡すのがマナーです。
ただし、人によっては結婚式を挙げないという場合や、ご祝儀を辞退する場合もあるので、柔軟な対応が必要になります。
ご祝儀はいらないと言われた場合は、お祝いのギフトなどを贈ると良いですよ。
兄弟・姉妹の結婚式でご祝儀を渡すタイミングは前もって直接手渡ししておくのがベター

ご祝儀の渡し方といえば、結婚式の受付で手渡しするのが一般的な渡し方ですよね。
でも、兄弟姉妹は「ゲスト」というより、「主催者側」の立場。ご祝儀も他のゲストと同じく受付で渡すのではなく、結婚式より前に渡しておくのが正解です。
結婚式の直前や当日は、新郎新婦も結婚式前でバタバタしている時期。そんな慌ただしい時期を避け、結婚式の1ヶ月前~1週間前くらいまでには渡しておくといいでしょう。その際に、お日柄を大事にするなら、大安などの吉日の午前中にするとさらに良いですよ。
渡し方としては、直接会って手渡しできるのがベスト。遠方に住んでいる場合や都合が合わない場合は、現金書留などで郵送してもOKです。
兄弟・姉妹へのご祝儀の渡し方

兄弟・姉妹へのご祝儀は、結婚式当日の受付ではなく、事前に渡すのが一般的です。渡し方にもいくつかポイントがあるので、確認しておきましょう。
披露宴の1ヶ月~1週間前までに手渡しする
兄弟・姉妹へのご祝儀は、披露宴の1ヶ月~1週間前までに渡すのがおすすめです。結婚式の準備で忙しい直前は避け、余裕を持って渡すようにしましょう。
直接会って手渡しするのが理想ですが、難しい場合は、下記の方法も検討してみてください。
遠方に住んでいる場合は事前に郵送する
遠方に住んでいる場合は、現金書留で郵送するのが良いでしょう。ご祝儀袋だけでなく、お祝いのメッセージカードを添えることで、より気持ちが伝わります。
郵送する際は、披露宴の2週間前までには届くように手配しましょう。
メッセージカードを添えて渡すと◎
ご祝儀を渡す際には、メッセージカードを添えるのがおすすめです。
結婚のお祝いの言葉に加えて、兄弟・姉妹との思い出や、新生活へのエールなどを書き添えると、より気持ちが伝わるでしょう。手書きのメッセージは、心のこもった贈り物になります。
兄弟への結婚式ご祝儀に関するよくある質問
兄弟姉妹の結婚式には、何かと疑問が生じるもの。ここでは、よくある質問とその回答をご紹介します。これで、あなたも安心して結婚式に臨めるはずです。
Q1.式なしの場合はいつ渡すと良いですか?
兄弟姉妹が結婚するけれど、結婚式は挙げないときは、ご祝儀はどうすればいいのでしょうか?
ご祝儀は結婚に対するお祝いの気持ちなので、結婚式をしてもしなくても贈るのが基本となります。
結婚式を挙げない場合でも、兄弟姉妹へのご祝儀は5万円程度が相場。ただし、兄弟姉妹なのできちんとお祝いがしたいという場合、結婚式がなくても7万円から10万円ほど贈る場合も少なくありません。
また、ご祝儀代わりに結婚祝いの品を贈るというパターンもあります。親族間で相談して、どうするかを決めると安心です。
Q2.結婚祝いを渡すのに良い日は?
結婚祝いを渡すのに特に良い日、縁起が良いとされる日は、「大安」「友引」「先勝」です。これらの日は、新しいことを始めるのに良い日とされており、結婚のお祝いにも適しています。
Q3.お祝いを渡してはいけない日はいつですか?
結婚祝いを渡すのに避けるべき日は、「仏滅」「赤口」です。
これらの日は、一般的に不吉な日、あるいは祝い事には向かない日とされています。特に、仏滅は六曜の中で最も悪い日とされているため、結婚祝いだけでなく、お祝い事全般を避けるのが良いでしょう。
まとめ:「ご祝儀」はそこにこめられた気持ちが大事
兄弟・姉妹の結婚は、人生における大きな喜びの一つです。ご祝儀はその喜びを分かち合い、新生活を応援する気持ちを伝える大切な手段です。この記事で紹介した相場やマナーを参考に、心のこもったお祝いを贈りましょう。そして、いつまでも仲の良い兄弟・姉妹でいてくださいね。
この記事の著者

スマ婚編集部
スマ婚編集部は、元プランナー、カウンセラーなどのメンバーにて、皆さんのパーティーや、結婚生活の役立つ情報や、最新情報をお届けいたします。InstagramやXでも情報発信をしておりますので、ぜひぜひプレ花嫁さまと繋がれたら嬉しいです。