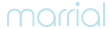「素敵なプロポーズが夢だった・・・・・・」
新婦の言葉がずっと胸に引っかかっていた。
彼女のために最高のプロポーズを演出してあげたい・・・・・・。
担当のウェディングプランナーが提案した“素敵なプロポーズ”とは一体!?
今よりもいくぶんか小さかったあの頃の僕らは、
ただひたすら無垢に、
何でも出来ると、
何にでもなれると思っていて。
あの頃よりも少しだけ大人になってしまった僕らは、
「世界」の「色々」が押し寄せて、
見たいものが見れずに、
見たくないものが見えすぎて、
ただ、この世界の外枠を、
自分自身の天井を、
決めつけて、諦めることを覚えてしまった。
こうかつな僕らは、
いつも理由をぶらさげて、
視線を落として、
線路から外れようとはしないんだ。
だからその、つぐんでしまった言葉を、
飲み込んでしまった望みを、
もう一度握りしめて、
旅に出よう。

パタリ。と本の表紙を閉じる。
ふぅ、と細い息を吐きながら空を仰ぐと、なんだかグルグルとしたものがみぞおちの奧で回って仕方がない。
物語の最後に綴られた詩は、今の自分に問いかけられているようで、もうしばらく感じていない、忘れてしまったいつかの自分の影を目の端に捉えた気がした。
——————「素敵なプロポーズが夢だったんですけどね」
先日、訪れて下さった一組のカップルの彼女が言っていた言葉をふと思い出す。彼女は諦めたように、自嘲するように、だけど決して重いわけではなく、ただひたすら軽く自分のかつての願いを口から落とした。
それは、普通ならば取りこぼしてしまうほど些細なものだったけれど、私の胸にはなぜかずっと引っかかっていて、その願いを叶えてあげたいと試行錯誤を続けていたのだ。
彼女を初めて見た時の印象は、「疲れているかもしれない」だった。
いつもなら、ワクワクと結婚式に思いを馳せた幸せそうなカップルを見ることが多いけれど、今回はなんだかそんな様子ではなく、その理由はすぐに察することが出来た。
彼女の横には可愛らしい女の子が遠慮がちにクリクリとした目をこちらに向けていたのだ。
彼女がその子を愛していないわけではない。むしろ、大切に思いすぎているくらいだ。けれど、彼女も親の前に一人の人間だから。初めての育児に、重なる疲労はもはや消化しきれずに滲み出ていく。
せめて、この場所にいる間は「彼女自身」を彼女が考えられるように。
私は会社の仲間に子供を見てもらうことを提案して、新婦様と新郎様はお二人がどのような結婚式をあげたいのかというお話に集中していただいた。
何度か新郎新婦様と打ち合わせを重ねていったが、新郎様に提案する「プロポーズの仕方」が思い付かない。
彼女が呟いたそれは、依然私の中で言葉のまま形にされることなく浮遊している。
「うーあー」
輪郭が定まらないまま、フツフツと想いだけが先走る。それが耐えきれずに思わず唸り声をあげると、
「うるさいんだけど」
と、ルームシェアをしている相方からピシャリと叩かれた。
「だぁってぇ」
「だぁってぇ、じゃない。大人になってそんな言葉遣いすんな」
あんたの言葉遣いもどうかと思うけど。相方の、人よりもいくぶんか男らしい所には口を出さず、私は再び音をあげる。
「あー、だって、思い付かない! 良いアイデア無い? なんか、こう、ガツーンと来るやつ!」
「ない。っていうか、あんたが何について言ってるのかがさっぱり分からん」
相方の冷めた物言いに、「真剣に悩んでるのにさ」と少しいじけたように言ってやると、隣から盛大なため息が聞こえた。
やばい。これは、本気で怒らせたかな?
チラリと横を盗み見ると、予想と反して彼女は柔らかい顔をしていた。「しょうがないな」と子供をあやす親のような。
「明日、仕事休みだろ。久しぶりにどっか行くか。気分転換。そしたら、なんか思いつくかもよ」
確かに、それは一理ある。が、出かけている時間よりも、真剣に考えた方がいい気がする。中々決められない私に痺れを切らすと、「じゃ、明日行くから」と、勝手に決められてしまった。
まぁ、いいか。
なるようになる。というお得意な考えを脳みそに貼り付けて、私はゆっくりと暗闇に意識を手放した。

「ねぇ、気分転換って言ったよね?」
「うん、言った」
「そしたら、普通、私の好きな所行かない?」
「いやぁ、そうとは限らない。要は、気分が転換すればいいわけだから」
私は、ショッピングが好きだ。実際に買わなくても、見るだけでも充分心が癒される。だから今回もきっと、彼女は私をショッピングに連れて行ってくれるのだろうと思ったんだが。
次の日、彼女に連れられて行ったのは町の小さなギャラリーだった。
彼女は芸術が好きで、よく一人でそういう場所に行っているのは知っていたけど、まさか自分がそこに連れて行かれるとは思っていなかった。
案の定、予想した通り私が先に見終わり、没頭している相方を外で待っていることになった。
こういう時。ひどく時間がゆっくり進む気がして、それと同時に普段私たちがどれだけ「時」の奴隷になっているかが分かる。
だけど、だからこそ、記念日が大切になってくるんだ。
「やっぱり、最高のプロポーズにしてあげたいよなぁ」
と、ふいに背中に衝撃が走った。
見ると、可愛らしい男の子がしがみついている。
「ゆ、ゆうかお姉ちゃん!」
ふるふると震えながら伏せた顔に真っ赤な耳が映えている。
「僕、どうしたの? 私、ゆうかお姉ちゃんじゃないと思うよ?」
ハッとしたようにその子が顔を上げると、ただでさえ赤い顔がさらに真っ赤になった。
「ご、ごめんなさい!緊張してて、前見てなくて……」
「大丈夫だよ。ゆうかお姉ちゃん探そうか?」
「ううん、いい……多分、先帰っちゃったんだと思う。どうせ、隣の家だし、大丈夫」
そう少しだけ安心したような顔をした男の子の手には、ぎゅっと握りしめられていた赤い一本のバラがその存在を主張していた。
「そのバラ……」
「す、好きって、伝えるのは赤いバラが一番良いって兄ちゃんが言うから……」
さすがに、恥ずかしさに耐えられなくなったのか、その場からその子が走り去ると、ちょうど相方が戻ってきたところだった。
「悪い、終わったよーって、大丈夫? なんかぼーっとしてない?」
「バラ……か」
「へ?」
「ごめん! ちょっと、アイディアまとめたいから先帰るわ! ほんとゴメンね! ありがとう!」
置き去りにした相方をチラリと振り返ると、唖然とした顔をしていて少しだけ笑ってしまう。
そのあと、私は家に帰ると早速アイディアをまとめはじめた。

大きく下がるスクリーン。
白いドレスに包まれた彼女は、目を丸くしてそのスクリーンを見つめていた。
そして、一枚の画がそのスクリーンのスタートを切る。
ご家族から、ご友人から、順々に手渡されていくバラ。
一本。また一本と赤が集まり、優美に重なり合う花びら達が手を繋いで輪になっていくかのように、赤が広がる。
それは思いと一緒に。
あの日、置き忘れた「夢」と一緒に。
新郎様の手の中に集まった沢山の赤い想いは、スクリーンの暗転と共に暗闇に溶け、そして、新婦様の前に再び形を成して現れた。
真っ赤なバラの花束を抱えた新郎様と、そして、新婦様と同じドレスを纏ったお二人の一番大切なお子様。
彼女の目から大きな粒が頬を伝い、白が飲み込んでいく。
「僕と結婚してください。これからも三人で幸せに暮らしていきましょう」
涙で埋もれるなかに、今までに無いくらいの満面の笑顔。
もう、最初のような疲れた顔はそこにはなかった。

いつか。彼女が置いてきてしまった「夢」。
無意識のうちに見て見ぬふりをしてきたあの日の自分。
もし、誰かが自分で自分の天井を決めつけてしまうなら、私はその囲いの外を見せよう。もし、視線を落として、線路から外れようとしないなら、私はその肩を叩いて一緒に空を仰ごう。
きっと、今日の彼女のように。