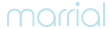親子だからこそ、本音でぶつかれないときがある。
結婚式という人生の大イベントは、普段言えない思いを伝えるチャンスかもしれません。
いつもより味噌汁がしょっぱい理由は・・・・・・?
読み終わった後、両親に連絡したくなります。
ガシャーン!
ガラスの割れる音。弾ける音。割れた破片が手にかすったのか、地面に赤い染みを二つ、三つ作る。でも、痛くない。痛くない。感覚が、フィルターを一枚通したかのように鈍い。それに伴って、聞こえてくる音も鈍い。
「———どうして、あんたはいつも————そんなんだから——————」
雑音。雑音。
ヒステリックな声が、言葉にはならずに耳に入る。
こんなのは、全部雑音だ。
だから、大丈夫。
「いってきます……
」
家に響き渡る母の甲高い声をその扉で閉じ込めて、私はケガをした手の手当もせずに、仕事に向かう。
大丈夫。この扉を閉めれば、全部見えなくなる。私は私でいられるから。

「テーブルクロスのお色は、新婦様のカラードレスが決まったら、それに合わせて決めていきましょうね!」
式の準備は順調に進んでいた。
新郎も新婦もとっても優しい方で、お会いするとなんだかこちらがホッとしてしまうくらいだ。
ウェディングプランナーは接客業の中でも、お客様の人生の深いところに触れる仕事だ。人の感情を揺さぶるためには、その人の記憶の奥へと潜り込む必要がある。人の数だけ人生があるってよく言うけど、実際にその様々な人生たちを目の当たりにすると、本当にその意味がよく分かる。
そして、その度に、自分の人生も目の当たりにする。
浮き彫りになる。
新婦はいわゆる理想的な、家族の模範のような家庭で育ったらしい。夕飯はいつも家族みんなで食卓を囲んで。父のボーナスが出た時は家族旅行で色々なところに出かけて、時にはその旅行のために学校を休むこともあったという。
一方、新郎は幼い頃に両親が離別していて、母、姉、祖母と一緒に暮らしていたという。父親のいない寂しさと思春期がもらたすフラストレーションが入り混じり、時にそれらの矛先を母親に向けてけんかをすることも多かったと語っていた。
母も一人の人間だということ、大人になった今ならそのことがよく分かる。だけど、幼い自分はただ自分を父親のいない状況にした母に当たることでしか、自分を表現出来なかったから。あのころの母は、ひたすら強いものだとばかり思っていたから。
母親に素直になれないのは、まだあの頃のままだけど……と少し濁すように新郎は言った。
—————本音でぶつかりあえる家庭が理想なんです
声を揃えてそう言った新郎新婦の言葉で、胸が締め付けられた。
新郎は、私と似ている。
私も父と母が離別し、母が一人手で育ててくれた。
あの日、いつもと変わらない様子で「いってきます」と言った父。「今日は何時に帰ってくるの?」と無邪気に聞いた私に、「一緒に夜ご飯食べような」と頭を優しく撫でてくれた父。いつもより広く感じた部屋に違和感を覚えながら、その日、父親がもう帰ってこないなんて分からずに……私は父さんと一緒に夜ご飯を食べようと夜遅くまで待っていた。
母とのけんかが絶えなくなったのは、父がいなくなってからだった。幼い私も、疲れていた母親も。お互いがお互いを支えて、慰めて、癒すことが出来ずに、自分で処理しきれない感情を持て余して、ただ撒き散らすだけ。今さら普通に接することがどういうことなのか、分からない。
急に、朝の手の傷がズキズキと痛んだ。
気を抜いてしまうと思い出してしまう家のことを、頭を振って追い払うと、仕事の方に集中した。
今回私は新郎のお母様から新郎への手紙をサプライズに考えていた。そのことを先日新婦に提案したが、彼女は新郎のお母様の電話番号や、メールアドレスを知らず、協力をお願いするのは難しそうだ。
新郎のお母様には、私から話をしてみよう。
当日の新郎の喜ぶ顔を想像して、自然と笑みがこぼれた。

「ただいま」
家の玄関を開けると、また私の時間が進む。
今朝のガラスの破片はそのまま。
母さんは、その散らばった棘の中でただ呆然と座り込んでいた。
「今片付けるから、そのまま座ってて」
手際よく片付けていく。
これでもう何枚お皿を割ったのか。
見慣れた光景に、なんの感情も浮かんではこなかった。
母さんの近くの破片を片付けようと手を伸ばすと、その手首にそっと母さんの手が触れた。見上げると、少しだけ潤んだ瞳でこちらを見る。
こんな表情ももう見飽きてしまった。
—————しっかりしてよ
口を開きかけて、やめた。
今さら何を言おうというのだろう。どうにかしたいと思うのに、足が一歩前に進まない。自分が何かに絡め取られて、目隠しをされて、どこにいるかも分からないまま、黒いドロドロが腹の底に溜まっていく。
家族なのに、母さんが何を考えているのか、分からない。
私は何も言えずに、次の日同じようにまた仕事に向かった。

「新郎のお母様からお手紙の返事届いてますよ」
会社で朝一にそう聞いて、早速その手紙を開く。
きっと、これで親子の絆が……
「……えっ!」
一瞬思考が固まった。
—————私の息子は私を母親と認めてないでしょうし、きっと恨んでいると思います。ですので、私から手紙を書くのはやめておきます
視覚から入る言葉と、脳内で記憶された自分の母の声が重なった。
———恨んでいる
その言葉がまるで色がかかったように見える。
そんなことない。恨んでいるはずがない。
腹の底に溜まったドロリとしたものが、ヘソから流れ出す。
どうにかしたい。新郎は「恨んでいる」なんて思ってない。そんな風に思っていない。
けど……どうしよう……
私はもう一度、受話器に手を伸ばした。

「……ここで、ある方からのサプライズがございます……」
司会者の声が会場に響きわたる。
「……それは、なんと、新郎様からお母様へのお手紙のプレゼントです……」
会場が一気にざわつく。
先ほどまで通常運転だった心臓が徐々に加速していった。
大丈夫。大丈夫。きっと、上手くいく。
息を深く吸って、細く吐く。
新郎が前に出て、手紙を開く。心なしか手が細かく震えているように見えた。
「……母さんへ」
普段は言えないこと。言い逃してしまうこと。こんな機会がなければ一生伝えられないこと。素直じゃないから。素直になれないから。だから、せめて今日だけは……
手紙を読み進めるうちに、自然と新郎の目が潤んでくる。
ふと、新郎のお母様のお顔を見てハッとした。
何か、肩に乗った塊が綺麗に溶けていくような。救われたような。そんな穏やかで、優しい表情をして、涙を流していた。
きっと、ずっと心に引っかかっていたに違いない。
あの日。父親を失ったことで、自分が恨まれていないか。自分の選択は間違っていたんじゃないか。ちゃんと、子供を愛せていたのか。子供は愛されていると感じていたのか。
そんな苦しみの全てが報われた瞬間が、はっきりと目で見えた。
「母さん。今まで育ててくれてありがとう。母さんの子供に生まれて本当に良かったよ」
最後にそう締めくくられた手紙は、なんだか私の心にそっと落ちて、溶けていった。

「ただいま」
家のドアを開けると、なんだかいい香りが立ち込めていた。
良かった。今日は母さんの体調もいいみたいだ。
食卓には久しぶりの母さんの手作りの夕飯が並べられていて、それを二人で食べた。
母さんにバレないように一度大きく深呼吸をした。汗が背中を伝い、確かに座っているはずなのにお腹がフワフワしてしょうがない。
意識が今日の結婚式に飛ぶ。今日、確かに、込み上げてくる何かが感情を揺さぶって、言葉では言い表せないどうしようもない想いが溢れてきたのだ。
その想いの根源をもう私は知ってる。
グッと唾を飲み込むと同時に、喉に突っかかっていたご飯を胃に押し込む。ドクドクと波打つポンプがまるで喉にせり上がって来るかのように、先ほどまで開いていたはずの気管支を閉めて、首から上の血液を押しとどめた。一回箸を置いて、一呼吸。口を開いて、閉じる。そして、また、一呼吸……もう舌のつけ根に言葉は乗っているのに。私は息を大きく吸って、吐く息に言葉を乗せた。
「いつもありがとう。私、お母さんの子供で良かったって思ってるよ」
なんだか恥ずかしくなって、味噌汁に手を伸ばしかけて、はたと止まる。
見ると、母さんが口を抑えて静かに泣いていた。
いつものヒステリックな時の母さんとは違う。ちゃんと母さんの目は私を捉えていた。
そうか。母さんは、私が母さんの子供であることをどう思っているのか、自信が無かったんだ。だから、不安だったんだ。
「母さんも……あなたが生まれてきてくれて……本当に……嬉しかった……ありがとう……ありがとう…………」
その日の味噌汁は、なんだかいつもよりしょっぱくて、だけどなんだかいつもより沁みた。