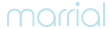【ウェディングストーリー①】お父さん、今まで育ててくれてありがとう
男で一つで育てられた新郎様。
結婚式当日新郎様は今まで育ててきてくれたお父様に
どのようにして感謝の気持ちを伝えられるのでしょうか…?
健、28歳。1カ月後には付き合って3年になる寛子との結婚式が控えている。チャキチャキと動いてくれる寛子のおかげで式の準備は順調で、直前となった今でも比較的穏やかな毎日を過ごしている。ふたりが挙げる式は、いたってオーソドックス。結婚式場に併設されたステンドグラスが美しいチャペルで挙式し、そのまま披露宴会場に移動して披露宴パーティーを行う。

演出も何か特別なことをするわけでもなく、ファーストバイトやキャンドルサービスなど、定番のプログラムを盛り込んだシンプルな内容だった。それはすべて、寛子の希望だった。寛子のお腹には6カ月の赤ちゃんがいる。あまり派手なことはせず、大切な人達とささやかなひと時を過ごすことが寛子の願いだった。健もそれで良かった。健にとっては、寛子が喜ぶ顔を見ることが何よりも優先すべきことだった。
「いいか、健。奥さんに毎日笑ってもらえるようにすることが、夫としての男の役目だからな」。
それは健の父親が、健がまだ小さい頃から口癖のように何度も口にしてきた言葉だった。そんな父親の影響で、健は幼い頃から、女性の笑顔は男が守るもの……そんなイメージをぼんやりと抱いていた。

健は自分の母親を知らない。健の母親は生まれつき心臓が弱く、健を妊娠する前には定期的に病院で検査を受けて薬を飲んでいた。妊娠は難しいかもしれない……そう諦めようと思った夫婦のもとに健がやってきた。医者のサポートを受けながらも、母は毎日幸せな日々を送っていたそうだ。健の名前は、健康の健。生まれつき病弱だった母は、お腹の子が男の子と分かった時、体が丈夫でたくましい男の子に育ってほしいという願いを込めて、健という名前をつけたいと父に相談してきたそうだ。
健を出産して2日後、母は心臓発作を起こしてこの世を去った。
それは本当に急な出来事で、つい数時間前までは元気に喋っていたそうだ。医者が言うには、健の出産で体に相当な負担がかかってしまっていたらしい。出産後、今まで受けていた定期診断を再開するたった2日前の出来事だった。

それから父は、再婚することもなく男手一つで健を育て上げた。トラックの長距離運転手をしていた父は、不在にする際には亡くなった妻の家に健を預けて面倒を見てもらっていた。家へ帰る頃にはいつも、健が好きなおやつを一つだけ、お利口さんに待っていたご褒美として持って帰ってきてくれた。
そうして事あるごとに、あの言葉を健に語り掛けていた。自身が妻に対してしてあげることができなかった後悔を、自分をいましめるかのように口にしていた。
愛する妻の死後、父がどれだけの深い悲しみを背負いながら生きてきたのか、幼い息子を育てるためにどれだけの苦労と努力をしてきたのか、子どもの頃の健には知るよしもなかった。当たり前のように進学させてもらい、当たり前のようにご飯を作ってもらい、中学、高校では、健の部活の応援もしてくれた。そんなあまりにも当たり前にあった父の愛情を、大人になった今、当たり前ではなかったのだとようやく気が付いた。
働くこと、お金を稼ぐこと、家事をすべて行うこと、家族に優しくすること、これらをすべて、文句も言わずただ黙々とこなしてきた父は、大した男だ。健は自分が結婚して夫と父親になる立場に立って、初めて父の偉大さを痛感した。そして若くして愛する妻を亡くすことがいかに辛いことか、今なら想像ができる。
「息子から父親に向けて感謝を伝える演出って、何かあったりするんですかねぇ……」
結婚式に関しては寛子の好きなようにすればいいとは言ったものの、健はどうしても、心にあるくすぶった感情を消化しきれずにいた。だからこうして、式の直前になってふたりの式を担当してくれているウェディングプランナーの由紀の元を訪れたのだ。
「いやぁ……何か……そんな大々的なものでなくっていいんです。シンプルなもので……。ただちゃんと、父親にありがとうって伝えるきっかけが欲しいっていうか……」
由紀はいつも、健と寛子の話を親身になって聞いてくれるウェディングプランナーだった。この式場で結婚式を挙げると決めた理由も、由紀のその人柄だった。寛子はまるで昔からの友人のように由紀のことを信頼し、式に関する相談はもちろん、家族のことや健とのことなど何でも話した。そのおかげで、由紀との打ち合わせがある日の寛子はいつもご機嫌だった。
寛子ほどではないにしても、健も由紀のことを心から信頼していた。定番でシンプルな式で良いと告げたふたりを理解しながらも、健と寛子ならではのスパイスをさりげなく盛り込んだ演出を提案してきてくれた。口数が多いわけでなく、どちらかというと常に聞き役に回りながらも要所要所で的を得た提案をする由紀のセンスの良さは話していてとても心地のいいものだった。
(由紀さんなら何とかしてくれるんじゃないか)。
健はそんな思いで、今からでも間に合う父親への感謝を伝える演出がないか、相談に訪れていた。

そして迎えた式当日。挙式も滞りなく終わり、披露宴も順調に進んでいる。宴が終盤に向かうに連れて、健の緊張は高まっていった。そして訪れた親進呈ギフトを渡すシーン。健は寛子と一緒に用意した両家の親へのギフトを渡す際、誰にも気づかれないよう父親にだけこっそり小さなボックスをプレゼントした。
不思議に思った父親は席に戻って箱を開けてみると、そこには、トラックの出張から帰る際にいつも買っていった、健の好物だったチョコレートがぎっしり詰まっていた。そしてそれらチョコレートの包装紙には、健が生まれた時から28歳になるまで、1年毎にその歳の健の姿がプリントされている。箱の底には、真っ白い二つ折りのカードが埋まっている。
「親父、今まで育ててくれてありがとう。母さんもきっと、親父の横でずっと笑顔だったと思います」。
何の装飾もないシンプルなそのカードを開くと、健の手書きでこの一言が添えられていた。
お世辞にもキレイとは言えない健の字だが、一文字一文字丁寧に書かれた様子が見てとれる。生まれたばかりで顔を真っ赤にして泣く0歳の健、幼稚園で初めて友だちができて嬉しそうな3歳の健、小学校にあがり、初めて試合でヒットを打つことができた時の健、中学校の運動会のリレーで一番になった時の健、そこには、これまでの健と父親の思い出がぎっしりと詰まっていた。その一つひとつを眺めながら、健の父は人知れず口を堅く結び、こみ上げてくる感情をのどの奥にぐっと飲み込んだ。

「必ず、お父さんと一緒の思い出の写真を選んでください」。
そうアドバイスをくれたのはウェディングプランナーの由紀だった。ぼんやりした健の相談を親身になって聞き、大げさじゃないけどとびきりのサプライズを提案してくれたのだ。
「二人の結婚式のプランナーが由紀さんでよかった」。プレゼントを渡した後、健は心の底から由紀に感謝した。
健はギフトを渡した後の父親の様子は知らない。だが由紀が、式場を後にする時にさりげなくその様子を教えてくれた。少し照れ臭さを感じつつも、自分なりに精一杯の感謝を伝えることができたことに健の心はすがすがしさで満たされていた。
「今度、親父と母さんとの思い出話でも聞いてみようかな」。
二次会に向かうタクシーの中で、健はそんなことをふと思ってぼんやりしていた。
「健、眠たいの!? しっかりしてよ、これから二次会なんだから!」
寛子からの声で、はっと現実の世界に引き戻される。顔を上げると、寛子はぼーっとしていた健を見て笑っている。
「いいか、健。奥さんに毎日笑ってもらえるようにすることが、夫としての男の役目だからな」。
幼い頃から何度も言われてきた父親の言葉を思い出して、寛子の笑顔をこの先も守ることを健は固く心に誓った。
【ウェディングストーリー②】 今日の味噌汁がしょっぱい理由
親子だからこそ、本音でぶつかれないときがある。
結婚式という人生の大イベントは、普段言えない思いを伝えるチャンスかもしれません。
いつもより味噌汁がしょっぱい理由は・・・・・・?
読み終わった後、両親に連絡したくなります。
ガシャーン!
ガラスの割れる音。弾ける音。割れた破片が手にかすったのか、地面に赤い染みを二つ、三つ作る。でも、痛くない。痛くない。感覚が、フィルターを一枚通したかのように鈍い。それに伴って、聞こえてくる音も鈍い。
「———どうして、あんたはいつも————そんなんだから——————」
雑音。雑音。
ヒステリックな声が、言葉にはならずに耳に入る。
こんなのは、全部雑音だ。
だから、大丈夫。
「いってきます……
」
家に響き渡る母の甲高い声をその扉で閉じ込めて、私はケガをした手の手当もせずに、仕事に向かう。
大丈夫。この扉を閉めれば、全部見えなくなる。私は私でいられるから。

「テーブルクロスのお色は、新婦様のカラードレスが決まったら、それに合わせて決めていきましょうね!」
式の準備は順調に進んでいた。
新郎も新婦もとっても優しい方で、お会いするとなんだかこちらがホッとしてしまうくらいだ。
ウェディングプランナーは接客業の中でも、お客様の人生の深いところに触れる仕事だ。人の感情を揺さぶるためには、その人の記憶の奥へと潜り込む必要がある。人の数だけ人生があるってよく言うけど、実際にその様々な人生たちを目の当たりにすると、本当にその意味がよく分かる。
そして、その度に、自分の人生も目の当たりにする。
浮き彫りになる。
新婦はいわゆる理想的な、家族の模範のような家庭で育ったらしい。夕飯はいつも家族みんなで食卓を囲んで。父のボーナスが出た時は家族旅行で色々なところに出かけて、時にはその旅行のために学校を休むこともあったという。
一方、新郎は幼い頃に両親が離別していて、母、姉、祖母と一緒に暮らしていたという。父親のいない寂しさと思春期がもらたすフラストレーションが入り混じり、時にそれらの矛先を母親に向けてけんかをすることも多かったと語っていた。
母も一人の人間だということ、大人になった今ならそのことがよく分かる。だけど、幼い自分はただ自分を父親のいない状況にした母に当たることでしか、自分を表現出来なかったから。あのころの母は、ひたすら強いものだとばかり思っていたから。
母親に素直になれないのは、まだあの頃のままだけど……と少し濁すように新郎は言った。
—————本音でぶつかりあえる家庭が理想なんです
声を揃えてそう言った新郎新婦の言葉で、胸が締め付けられた。
新郎は、私と似ている。
私も父と母が離別し、母が一人手で育ててくれた。
あの日、いつもと変わらない様子で「いってきます」と言った父。「今日は何時に帰ってくるの?」と無邪気に聞いた私に、「一緒に夜ご飯食べような」と頭を優しく撫でてくれた父。いつもより広く感じた部屋に違和感を覚えながら、その日、父親がもう帰ってこないなんて分からずに……私は父さんと一緒に夜ご飯を食べようと夜遅くまで待っていた。
母とのけんかが絶えなくなったのは、父がいなくなってからだった。幼い私も、疲れていた母親も。お互いがお互いを支えて、慰めて、癒すことが出来ずに、自分で処理しきれない感情を持て余して、ただ撒き散らすだけ。今さら普通に接することがどういうことなのか、分からない。
急に、朝の手の傷がズキズキと痛んだ。
気を抜いてしまうと思い出してしまう家のことを、頭を振って追い払うと、仕事の方に集中した。
今回私は新郎のお母様から新郎への手紙をサプライズに考えていた。そのことを先日新婦に提案したが、彼女は新郎のお母様の電話番号や、メールアドレスを知らず、協力をお願いするのは難しそうだ。
新郎のお母様には、私から話をしてみよう。
当日の新郎の喜ぶ顔を想像して、自然と笑みがこぼれた。

「ただいま」
家の玄関を開けると、また私の時間が進む。
今朝のガラスの破片はそのまま。
母さんは、その散らばった棘の中でただ呆然と座り込んでいた。
「今片付けるから、そのまま座ってて」
手際よく片付けていく。
これでもう何枚お皿を割ったのか。
見慣れた光景に、なんの感情も浮かんではこなかった。
母さんの近くの破片を片付けようと手を伸ばすと、その手首にそっと母さんの手が触れた。見上げると、少しだけ潤んだ瞳でこちらを見る。
こんな表情ももう見飽きてしまった。
—————しっかりしてよ
口を開きかけて、やめた。
今さら何を言おうというのだろう。どうにかしたいと思うのに、足が一歩前に進まない。自分が何かに絡め取られて、目隠しをされて、どこにいるかも分からないまま、黒いドロドロが腹の底に溜まっていく。
家族なのに、母さんが何を考えているのか、分からない。
私は何も言えずに、次の日同じようにまた仕事に向かった。

「新郎のお母様からお手紙の返事届いてますよ」
会社で朝一にそう聞いて、早速その手紙を開く。
きっと、これで親子の絆が……
「……えっ!」
一瞬思考が固まった。
—————私の息子は私を母親と認めてないでしょうし、きっと恨んでいると思います。ですので、私から手紙を書くのはやめておきます
視覚から入る言葉と、脳内で記憶された自分の母の声が重なった。
———恨んでいる
その言葉がまるで色がかかったように見える。
そんなことない。恨んでいるはずがない。
腹の底に溜まったドロリとしたものが、ヘソから流れ出す。
どうにかしたい。新郎は「恨んでいる」なんて思ってない。そんな風に思っていない。
けど……どうしよう……
私はもう一度、受話器に手を伸ばした。

「……ここで、ある方からのサプライズがございます……」
司会者の声が会場に響きわたる。
「……それは、なんと、新郎様からお母様へのお手紙のプレゼントです……」
会場が一気にざわつく。
先ほどまで通常運転だった心臓が徐々に加速していった。
大丈夫。大丈夫。きっと、上手くいく。
息を深く吸って、細く吐く。
新郎が前に出て、手紙を開く。心なしか手が細かく震えているように見えた。
「……母さんへ」
普段は言えないこと。言い逃してしまうこと。こんな機会がなければ一生伝えられないこと。素直じゃないから。素直になれないから。だから、せめて今日だけは……
手紙を読み進めるうちに、自然と新郎の目が潤んでくる。
ふと、新郎のお母様のお顔を見てハッとした。
何か、肩に乗った塊が綺麗に溶けていくような。救われたような。そんな穏やかで、優しい表情をして、涙を流していた。
きっと、ずっと心に引っかかっていたに違いない。
あの日。父親を失ったことで、自分が恨まれていないか。自分の選択は間違っていたんじゃないか。ちゃんと、子供を愛せていたのか。子供は愛されていると感じていたのか。
そんな苦しみの全てが報われた瞬間が、はっきりと目で見えた。
「母さん。今まで育ててくれてありがとう。母さんの子供に生まれて本当に良かったよ」
最後にそう締めくくられた手紙は、なんだか私の心にそっと落ちて、溶けていった。

「ただいま」
家のドアを開けると、なんだかいい香りが立ち込めていた。
良かった。今日は母さんの体調もいいみたいだ。
食卓には久しぶりの母さんの手作りの夕飯が並べられていて、それを二人で食べた。
母さんにバレないように一度大きく深呼吸をした。汗が背中を伝い、確かに座っているはずなのにお腹がフワフワしてしょうがない。
意識が今日の結婚式に飛ぶ。今日、確かに、込み上げてくる何かが感情を揺さぶって、言葉では言い表せないどうしようもない想いが溢れてきたのだ。
その想いの根源をもう私は知ってる。
グッと唾を飲み込むと同時に、喉に突っかかっていたご飯を胃に押し込む。ドクドクと波打つポンプがまるで喉にせり上がって来るかのように、先ほどまで開いていたはずの気管支を閉めて、首から上の血液を押しとどめた。一回箸を置いて、一呼吸。口を開いて、閉じる。そして、また、一呼吸……もう舌のつけ根に言葉は乗っているのに。私は息を大きく吸って、吐く息に言葉を乗せた。
「いつもありがとう。私、お母さんの子供で良かったって思ってるよ」
なんだか恥ずかしくなって、味噌汁に手を伸ばしかけて、はたと止まる。
見ると、母さんが口を抑えて静かに泣いていた。
いつものヒステリックな時の母さんとは違う。ちゃんと母さんの目は私を捉えていた。
そうか。母さんは、私が母さんの子供であることをどう思っているのか、自信が無かったんだ。だから、不安だったんだ。
「母さんも……あなたが生まれてきてくれて……本当に……嬉しかった……ありがとう……ありがとう…………」
その日の味噌汁は、なんだかいつもよりしょっぱくて、だけどなんだかいつもより沁みた。

【ウェディングストーリー③】世界の片隅を灯す愛
参加者は親族のみでたったの「9名」。
翼さんと尚美さんが迎える結婚式は、両家初めての顔合わせでもあるのだとか。
ウェディングプランナーとして、二人のために提案できる最高の演出とは何か・・・・・・。
ウェディングプランナー陽子が考えた演出とは一体!?
新婦側、出席者4名。新郎側、出席者3名。新郎新婦を合わせて計9名。
これが、ウェディングプランナー2年目の陽子が本日担当する結婚式の全列席者。

こぢんまりとしつつも上品さに包まれた部屋に全員が会し、中央に置かれた大きなテーブルを挟んで向かい合って座っている。そしてお誕生日席には、新郎新婦が仲良く肩を並べている。
陽子の今日の結婚式での役割は「何もしない」こと。決して怠けているわけではない。全部で9名の結婚式。他人の陽子が目立てば気を遣わせてしまうだろうというプランナーとしての配慮だ。
「友人たちとは、カジュアルなお披露目パーティーをしたいと思うんです。なので、結婚式は本当に家族だけでしたいなと思ってるんですけど……」。
半年前、会場見学を終えた後の相談会で、新郎・翼が陽子の前で不安そうにこう話した。
「最近は、家族だけで式を挙げられる方もたくさんいらっしゃいますよ」。
穏やかな笑顔を見せて、陽子が答える。小さく息を吐いて、新婦・尚美が歯切れが悪そうにこう続けた。
「それが……、私たちを入れて9名なんです。」
話を聞くと、翼は秋田の出身で尚美の出身は香川。互いの家族をどちらかに呼ぶには負担が大きく、中間地点である東京に集まってもらいたいと考えていること。距離の問題から顔合わせ食事会も実現していないので、結婚式は顔合わせも兼ねているということ。
「この先、お互いの家族が集まる機会もそんなにないと思うんです」。
ふたりの願いは、結婚式で互いの家族同士の交流を深めることだった。離れて暮らしているからこそ、しっかりとした絆で結ばれたいと話してくれた。
「9名か……」。

その日の夜、陽子はお風呂につかりながら、翼と尚美のことを考えていた。最近は家族だけで式を挙げるカップルが多いと伝えたものの、9名は想像以上に少ない人数だった。ふたりの気持ちは聞いたものの、結局相談会の中では具体的な提案をすることができず、こうして湯船の中で悶々としている。ウェディングプランナー2年目の陽子にとっては、少しハードルの高いテーマだった。
「結婚式って、なんのために挙げるんだっけ」。
鼻まで湯船に浸かり、口先を尖らせて勢いよく息を吐く。ボコボコっと音を立てて目の前に泡ができる。
陽子は今まで担当した数々の結婚式を思い出していた。脳裏には、新郎新婦、その家族やゲスト達の幸せそうな笑顔が浮かんでくる。そしてそのどれもが、多くのゲストに囲まれている。それが9名となると、どんな雰囲気になるんだろう……。
「私だったら……私だったら……」。
人を喜ばせたい時は、まず相手のことを十二分に理解することから。これは、陽子がウェディングプラナーとして心がけてきた姿勢。
相手を理解するために、まずは相手の立場に立って物事を考えてみる。そしてこれは、たくさんのカップルとの打ち合わせを積み重ねてきた中で自然と身についたワザだった。
お風呂から上がり、濡れた髪を乾かしながらも、陽子はまだ9名での結婚式について考えていた。そして髪を乾かし切った後、陽子は意を決して、尚美がプロフィール欄に記入していたアドレス宛に一通のメールを送った。
「おふたりの家のご縁が結ばれ、新しい家族が誕生する。
そんな瞬間が実感できる結婚式を、一緒につくりましょう!」
尚美から賛同と共に喜びの声が盛り込まれた返事をもらうまでに、時間はそうかからなかった。
そして今、互いの家族が結婚式と初めての対面の日を同時に迎えている。
「新しい家族が始まる1日を“真っ白”な気持ちで迎えよう」
そう願いを込めて、出席者のドレスコードは全身白。白であれば、きれい目な平服でも良しとした。新婦・尚子の母親は上下セットになった白のツイードスーツ。父はレンタルした白のスーツで、ジャケットの代わりにベストを羽織り、香川県から出てきた田舎のおじさんとはかけ離れた、少しこなれた雰囲気を醸し出している。新婦尚子の2人の妹は丈が長めの白のワンピースを着用し、それぞれアクセントとして付けたパールのネックレスとイヤリングがよく似合っている。
一方、新郎・翼の母親はシフォンが軽やかに揺れる白のティアードワンピ―ス、父親は尚美の父親と同様に白のスーツだが、こちらはサスペンダーをアクセントとして利用している。翼とウリふたつの3歳違いの弟は、白シャツに白のハーフパンツで今風だ。
そしてもちろん、新郎新婦の翼と尚美も全身白。部屋中が白で包まれ、9名と少数ながらに、独特で強いオーラが放たれている。
「真っ白ですね」。
「ええ、真っ白ですね」。
笑いながらも、親同士はまんざらでもなさそうだ。
ドレスコードを“全身白”にしようというのは、ウェディングプランナー陽子のアイデア。白は「始まり」や「祝福」の意味を持つ色。初めて顔を合わせた家族同士に、なるべく早く打ち解けてほしい。そんな思いからの提案だったが、翼と尚美は喜んでそのアイデアを受け入れてくれた。

「あら、香川のうどんを使ったメニューがある!」
「私たちも、秋田のきりたんぽを食べるのは初めてです」。
「メニューに互いの地元の料理を盛り込む」。それも陽子からふたりへ提案し、料理長に掛け合って実現することができた。式で出される料理のメニュー表を見た家族から、陽子が意図していた通りの会話に、喜びでついつい頬がゆるんでしまう。
料理をきっかけに、互いの地元自慢の話しで会話に花が咲いている。それはまるで結婚式というよりも、ある家族の食卓のワンシーンのようだ。特別なプログラムは特に準備していないにも関わらず、“家族にとっては特別な料理”が運ばれるにつれて、会話も盛り上がっていく。

「家同士のご縁が結ばれ、新しい家族が誕生する」
少し離れた場所から9名の様子を見ていた陽子の頭には、今まで何度も繰り返し唱えてきた今日という日のテーマが浮かぶ。
そして陽子は、新しい家族の誕生をその目で確かに確認した。それはまるで、世界の片隅が暖かな光で灯されているような光景だった。
「結婚式って、なんのために挙げるんだっけ」。
この問いに対する答えが1つではないことを、今回のふたりの式を通して陽子は知ることができた。カップルの数だけ、答えがあるのだ。
「だから私のやるべきことは、世界の片隅を照らす愛情に包まれたカップルと家族を少しでも増やすこと」。
この日をきっかけに、陽子はウェディングプランナーとして新しい目標を追いかけていくことを決意した。
【ウェディングストーリー④】新郎様、その眩しい笑顔いただきました!
「僕は、来てくれたみんなが楽しんでくれればそれで……」。
新郎のたかしは口数が少なく、結婚式にとくに希望はない。
新婦のあきこさんは一人で盛り上がっていることを申し訳なさそうにし、たかしに気を遣う。
初めはそんな様子だった二人が、ウェディングプランナーの提案により、
結婚式当日をとても楽しみにするようになり、いよいよ当日を迎えます……!

「さぁ皆さんご注目ください! “ウェディングケーキ”の入場です!
会場内にはシャッター音が響き、驚きと感動の笑顔がどっと溢れ出す。
(やったぁーーーーー!!!)
狙い通りの反応に、声にならない声を胸に響かせる。
すかさず新郎新婦の表情を確認すると、二人もこちらを見て満面の笑顔を見せてくれた。肩が上がるくらいに鼻で大きく息を吸い、「ふぅーっ」とゆっくり吐き出していく。吐く息と同時に、体の内側で固まっていた緊張も流れ出ていくのを感じる。
この大々的なアナウンスと共に入場したウェディングケーキが、今回のストーリーの主役。四角いキャンバスに空港をイメージしたアートが施されていて、マジパンで作られた立体的な飛行機が一番の見どころだ。ピスタチオで表現された滑走路の芝生も、いい感じに空港間を演出している。
「ふたりに結婚準備をもっと楽しんでもらいたい」。そんな思いから提案した、空港をテーマにしたウェディングケーキの制作と入場のプログラム。紗季がイメージしていた通り、大盛り上がりの演出となった。
もう一度大きく息を吸い、今度は力強く一気に吐く。その時は「この瞬間がふたりの記憶に深く刻まれますように」と、ただただ心の中で願っていた。

ウェディングプランナー歴7年の紗季のモットーは“結婚式の準備期間中からカップルに楽しんでもらう”こと。紗季自身ウェディングプランナーという仕事をしているにも関わらず、自身が結婚式を挙げた時は、準備期間中に相手の家族や自分の家族の事を考えたり、決めることややることが多くて時間に追われたりと、少し疲れてしまった経験があった。
それ以来、自分が担当するカップルにはなるべくリラックスしてもらい、準備期間から二人で楽しんで取り組めるような打ち合わせとプランニングを意識していた。
「僕は、来てくれたみんなが楽しんでくれればそれで……」。
そんな時に紗季に相談にやってきたのがたかしとあきこだった。新郎のたかしは口数が少なく、打ち合わせ中に何を提案しても薄い反応が帰ってきた。一方新婦のあきこは笑顔が絶えず、結婚式に憧れを持っていると話していたが、一人で盛り上がっていることを申し訳なさそうにし、たかしに気を遣っているような感じだった。
(たかしさんが盛り上がれば、あきこさんだって気兼ねなく楽しむことができるはず)
結婚式に対するふたりの温度差を少しでもなくしたい一心で、4回目での打ち合わせはたかしの趣味について深く探ってみることにした。そこで出てきたキーワードが「飛行機」。話を聞いていくうちに、どうやらたかしは、大の飛行機好きであるということが判明したのだ。

ふたりのデートは空港での食事や飛行機を見に行く事も多かったと話すたかしの表情は急にイキイキしだし、心の底から飛行機を愛していることが一目瞭然だ。
(これは、活かすっきゃない)。
二人が共通して盛り上がるテーマは飛行機以外にない。そう確信した紗季は、次の打ち合わせで、結婚式のテーマを空港と飛行機にしてプログラムしていくことを提案した。
「何か……楽しそうですね。うん。……やってみたいです!」
ふたりにとっては想像もつかなかった「空港と飛行機をテーマにしたウェディング」。これまでは何となくというふんわりとしたイメージで進めてきた打ち合わが、この日を境にふたりにスイッチが入ったかのように、大きく前進しだした瞬間だった。そしてこの日は「結婚式のケーキは空港をイメージして作ろう!」と3人の意見が乗りに乗って一致し、打ち合わせを終えた。
「飛行機のイメージなんですけど……こんなのってどうですかね……?」

次回の打ち合わせで紗季にとって嬉しいサプライズが訪れた。今まで、たかしの笑顔は数えるほどしか見た事がなかったが、この日の打ち合わせではよく笑っている。そして何より、飛行機のイメージを膨らませるための写真を家から探し、何枚も持参してくれたのだ(!)。
楽しそうに話すたかしの様子に、隣に座っていた新婦のあきこもにこにこ笑顔を浮かべて頷いている。
(そうそう、これこそが私が望んでいたカップルの理想の姿!結婚準備期間も、楽しんでもらわないとね!)
自分たちの結婚式を心待ちにしているふたりの様子を目の前にした紗季は、今まで何度も感じてきたけれど、何度感じても飽きる事のない気持ちで心がぽかぽか満たされていくのを感じた。
正直、「空港と飛行機をテーマにしよう!」と提案したのはいいものの、紗季にとっても何もかも初めての経験で、決して簡単なものではなった。特に一番難しかったのがウェディングケーキのデザイン。ケーキを作るパティシエにとっても初めてのオーダーということもあり、滑走路や建物など、どんな材料を使うか、どんなイメージにするかなど、毎日必死にアイデアを絞り出してパティシエとの打ち合わせを重ねてった。
どうしても良いイメージの素材を見つけることができなかった場合には、たかしとあきこと打ち合わせた内容を細かくイラストにして伝えることもあった。
こうして、たかしとあきこ、そして紗季のありったけの想いをパティシエに託して迎えた結婚式当日! オリジナルケーキに見本はないので、3人にとってもこれが初めての対面となる。
「さぁ皆さんご注目ください! ウェディングケーキの入場です!」
祈るような気持ちでその瞬間を迎えた瞬間、紗季の目に映ったのは、喜んでシャッターを押し続けるゲストと目を丸くして驚く笑顔たち。アナウンスに紹介されて入場したケーキには、大きな拍手さえも贈られたのだ(笑)。
(やったぁーーーーー!!!)
期待以上のその反応に胸をなでおろしつつ、肝心なたかしとあきこに目をやると、ふたりも満面の笑顔でこちらを見て頷いている。

初めて打ち合わせに来た日、「喜んでもらえれば何でも良いんで……」と言っていたたかしがこんなに眩しい笑顔が見せてくれる日がくるなんて、あの日の紗季には全く想像もつかなかった。
(だから、ウェディングプランナーはやめられない!)
どんなに大変な思いをした準備でも、このふたりの最高の笑顔が全て帳消しにしてくれる。紗季にとってもまた、ウェディングプランナーとしてのやりがいを改めて噛み締めることのできた、忘れられない一日となった。
【ウェディングストーリー⑤】あの日の忘れもの
「素敵なプロポーズが夢だった・・・・・・」
新婦の言葉がずっと胸に引っかかっていた。
彼女のために最高のプロポーズを演出してあげたい・・・・・・。
担当のウェディングプランナーが提案した“素敵なプロポーズ”とは一体!?
今よりもいくぶんか小さかったあの頃の僕らは、
ただひたすら無垢に、
何でも出来ると、
何にでもなれると思っていて。
あの頃よりも少しだけ大人になってしまった僕らは、
「世界」の「色々」が押し寄せて、
見たいものが見れずに、
見たくないものが見えすぎて、
ただ、この世界の外枠を、
自分自身の天井を、
決めつけて、諦めることを覚えてしまった。
こうかつな僕らは、
いつも理由をぶらさげて、
視線を落として、
線路から外れようとはしないんだ。
だからその、つぐんでしまった言葉を、
飲み込んでしまった望みを、
もう一度握りしめて、
旅に出よう。

パタリ。と本の表紙を閉じる。
ふぅ、と細い息を吐きながら空を仰ぐと、なんだかグルグルとしたものがみぞおちの奧で回って仕方がない。
物語の最後に綴られた詩は、今の自分に問いかけられているようで、もうしばらく感じていない、忘れてしまったいつかの自分の影を目の端に捉えた気がした。
——————「素敵なプロポーズが夢だったんですけどね」
先日、訪れて下さった一組のカップルの彼女が言っていた言葉をふと思い出す。彼女は諦めたように、自嘲するように、だけど決して重いわけではなく、ただひたすら軽く自分のかつての願いを口から落とした。
それは、普通ならば取りこぼしてしまうほど些細なものだったけれど、私の胸にはなぜかずっと引っかかっていて、その願いを叶えてあげたいと試行錯誤を続けていたのだ。
彼女を初めて見た時の印象は、「疲れているかもしれない」だった。
いつもなら、ワクワクと結婚式に思いを馳せた幸せそうなカップルを見ることが多いけれど、今回はなんだかそんな様子ではなく、その理由はすぐに察することが出来た。
彼女の横には可愛らしい女の子が遠慮がちにクリクリとした目をこちらに向けていたのだ。
彼女がその子を愛していないわけではない。むしろ、大切に思いすぎているくらいだ。けれど、彼女も親の前に一人の人間だから。初めての育児に、重なる疲労はもはや消化しきれずに滲み出ていく。
せめて、この場所にいる間は「彼女自身」を彼女が考えられるように。
私は会社の仲間に子供を見てもらうことを提案して、新婦様と新郎様はお二人がどのような結婚式をあげたいのかというお話に集中していただいた。
何度か新郎新婦様と打ち合わせを重ねていったが、新郎様に提案する「プロポーズの仕方」が思い付かない。
彼女が呟いたそれは、依然私の中で言葉のまま形にされることなく浮遊している。
「うーあー」
輪郭が定まらないまま、フツフツと想いだけが先走る。それが耐えきれずに思わず唸り声をあげると、
「うるさいんだけど」
と、ルームシェアをしている相方からピシャリと叩かれた。
「だぁってぇ」
「だぁってぇ、じゃない。大人になってそんな言葉遣いすんな」
あんたの言葉遣いもどうかと思うけど。相方の、人よりもいくぶんか男らしい所には口を出さず、私は再び音をあげる。
「あー、だって、思い付かない! 良いアイデア無い? なんか、こう、ガツーンと来るやつ!」
「ない。っていうか、あんたが何について言ってるのかがさっぱり分からん」
相方の冷めた物言いに、「真剣に悩んでるのにさ」と少しいじけたように言ってやると、隣から盛大なため息が聞こえた。
やばい。これは、本気で怒らせたかな?
チラリと横を盗み見ると、予想と反して彼女は柔らかい顔をしていた。「しょうがないな」と子供をあやす親のような。
「明日、仕事休みだろ。久しぶりにどっか行くか。気分転換。そしたら、なんか思いつくかもよ」
確かに、それは一理ある。が、出かけている時間よりも、真剣に考えた方がいい気がする。中々決められない私に痺れを切らすと、「じゃ、明日行くから」と、勝手に決められてしまった。
まぁ、いいか。
なるようになる。というお得意な考えを脳みそに貼り付けて、私はゆっくりと暗闇に意識を手放した。

「ねぇ、気分転換って言ったよね?」
「うん、言った」
「そしたら、普通、私の好きな所行かない?」
「いやぁ、そうとは限らない。要は、気分が転換すればいいわけだから」
私は、ショッピングが好きだ。実際に買わなくても、見るだけでも充分心が癒される。だから今回もきっと、彼女は私をショッピングに連れて行ってくれるのだろうと思ったんだが。
次の日、彼女に連れられて行ったのは町の小さなギャラリーだった。
彼女は芸術が好きで、よく一人でそういう場所に行っているのは知っていたけど、まさか自分がそこに連れて行かれるとは思っていなかった。
案の定、予想した通り私が先に見終わり、没頭している相方を外で待っていることになった。
こういう時。ひどく時間がゆっくり進む気がして、それと同時に普段私たちがどれだけ「時」の奴隷になっているかが分かる。
だけど、だからこそ、記念日が大切になってくるんだ。
「やっぱり、最高のプロポーズにしてあげたいよなぁ」
と、ふいに背中に衝撃が走った。
見ると、可愛らしい男の子がしがみついている。
「ゆ、ゆうかお姉ちゃん!」
ふるふると震えながら伏せた顔に真っ赤な耳が映えている。
「僕、どうしたの? 私、ゆうかお姉ちゃんじゃないと思うよ?」
ハッとしたようにその子が顔を上げると、ただでさえ赤い顔がさらに真っ赤になった。
「ご、ごめんなさい!緊張してて、前見てなくて……」
「大丈夫だよ。ゆうかお姉ちゃん探そうか?」
「ううん、いい……多分、先帰っちゃったんだと思う。どうせ、隣の家だし、大丈夫」
そう少しだけ安心したような顔をした男の子の手には、ぎゅっと握りしめられていた赤い一本のバラがその存在を主張していた。
「そのバラ……」
「す、好きって、伝えるのは赤いバラが一番良いって兄ちゃんが言うから……」
さすがに、恥ずかしさに耐えられなくなったのか、その場からその子が走り去ると、ちょうど相方が戻ってきたところだった。
「悪い、終わったよーって、大丈夫? なんかぼーっとしてない?」
「バラ……か」
「へ?」
「ごめん! ちょっと、アイディアまとめたいから先帰るわ! ほんとゴメンね! ありがとう!」
置き去りにした相方をチラリと振り返ると、唖然とした顔をしていて少しだけ笑ってしまう。
そのあと、私は家に帰ると早速アイディアをまとめはじめた。

大きく下がるスクリーン。
白いドレスに包まれた彼女は、目を丸くしてそのスクリーンを見つめていた。
そして、一枚の画がそのスクリーンのスタートを切る。
ご家族から、ご友人から、順々に手渡されていくバラ。
一本。また一本と赤が集まり、優美に重なり合う花びら達が手を繋いで輪になっていくかのように、赤が広がる。
それは思いと一緒に。
あの日、置き忘れた「夢」と一緒に。
新郎様の手の中に集まった沢山の赤い想いは、スクリーンの暗転と共に暗闇に溶け、そして、新婦様の前に再び形を成して現れた。
真っ赤なバラの花束を抱えた新郎様と、そして、新婦様と同じドレスを纏ったお二人の一番大切なお子様。
彼女の目から大きな粒が頬を伝い、白が飲み込んでいく。
「僕と結婚してください。これからも三人で幸せに暮らしていきましょう」
涙で埋もれるなかに、今までに無いくらいの満面の笑顔。
もう、最初のような疲れた顔はそこにはなかった。

いつか。彼女が置いてきてしまった「夢」。
無意識のうちに見て見ぬふりをしてきたあの日の自分。
もし、誰かが自分で自分の天井を決めつけてしまうなら、私はその囲いの外を見せよう。もし、視線を落として、線路から外れようとしないなら、私はその肩を叩いて一緒に空を仰ごう。
きっと、今日の彼女のように。